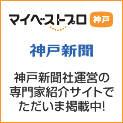こころを描いた映画・書籍の紹介コラム ~子どもの世界を描いた作品~
人生や心模様を描いた映画や書籍は数多くあります。しかしそれをすべて鑑賞することは困難。しかしさまざまな分野の障害やこころ模様について知ることや思いをはせることは、そこに描かれた登場人物の苦しみや葛藤に寄り添いながら、周り回って自分自身の問題への視点を広げ、深めることにつながります。以下は岸井がこれまで観賞したり読んできた映画や書籍・マンガなどの簡単な紹介です。もし興味を持たれたり、作品に触れる機会があった時に参考になれば幸いです。
*なお取り上げた作品は、あくまでもこれまでに岸井が観賞した作品です。現在観賞可能な作品とは限らず、過去のDVDなども紹介しています。また言うまでもなく岸井の興味の観点からの紹介ですので、作品の良しあしとは全く関係がありません。ご了解ください。
甘酸っぱさと共に、底知れぬ❝魔❞の広がる子どもの世界
少年は物語によって「母の死」を受け入れる 『怪物はささやく』
母親の死を目の前にして、しかし本当のことを知らされない、あるいか感じていても口に出すことは決してできない少年コナー。実際コナーにとって母親の死という現実はとてもそのまま受け入れられるものではありませんでした。しかし受け入れられないからと言って現実は変わりません。こういう時、人はどうやって現実と関わることが出来るでしょう?
この問題はコナーに限らず、私たち自身の人生において誰も目を背けることができない問題です。しかし、「なぜこの私が、この世に生まれてこれたのか?」という問いと同様、「なぜこの私が、死ななければいけないのか?」「なぜあなたが死ななければいけないのか?」と言う問いかけも明確に答えられる人はいないでしょう。
なぜなら「人はどうやってこの世に生まれてくるのか?」と言う問いや「死ぬとはどういうことか?」という問いは、科学的で一般的な問いかけではなく、寄りにも拠って「なぜこの私が」「なぜあなたが」、そして寄りにも拠って「なぜ今?」「なぜここで?」という一回性で個別性の問いかけは科学が答えられる問題ではないからです。
それにこたえられるのが「物語」なのです。「物語」は科学的な思考のように客観的な説明を必要としません。それを読んだ人がそれぞれ自分なりの解釈と意味と奥行を産み出すことができる生命の源のようなものです。
物語を通じて私たち人間は、自分の力や理解の限界を超えた現象を受け入れてきたのです。この映画でもコナー少年は母親の死という現実や学校におけるいじめや理不尽な現実に対して、自分なりの物語を作り出すことで「逃れることができない現実と向き合うための物語」を産み出し、乗り越えていきました。
見てはいけないようなものを見てしまったような・・・・
『悪の種子』

昨今どうしてあれほどの残酷で冷酷な行為が出来るのだろうか、と思わずにはいられないような事件がメディアを騒がせていますが、実は今回取り上げたDVD「悪い種子」も見終わって心が冷たくなんともやりきれなくなり、見てはいけないものを見たようなやりきれない思いにさせられた映画でした。
このDVDのカバーに載っている金髪のおさげの女の子の顔を良く見てください。この目つきを見るだけで伝わってくる何ともいえない冷たさ、あくどさ、はどうでしょう。(ただし断っておきますが、この子役の女の子自身ではありませんよ。あくまでもこの表情は演技なのですよ)
自分が欲しいもののためなら、友達も近所のおばさんも殺してしまう。それも少女とは思えないほどの巧妙で冷酷な手口で・・・・・それを悟られた使用人の男性も放火され殺される・・・・・しかし両親や身近な人の前では、優等生で明るい屈託のない可愛いおさげの少女なのです。
何なんだ、この表裏は???
「行為障害」というような言葉も浮かんできますが、そういうことよりも、見ているだけでぞっとしてこちらの心が冷え冷えとしてしまうような少女。今から60年以上も前に(原作は1954年、映画公開は1957年)すでにこういう子どもたちの存在が取り上げられていたとは・・・・・・。決して楽しい映画ではありませんが、現代という時代を見直すためにも、一見の価値はあるかもしれませんよ。
イマージナリーフレンドとの別れ
『ポビーとティンガン』

これはなかなか印象に残った秀作でした。テーマは、少女の「イマジナリー・フレンド」との別れ。「イマジナリー・フレンド」というのは、文字通り「空想の中の友人」ですが、はジブリの「思い出のマーニー」なんかにも通じる成長期の少女の繊細な世界に現れる存在です。そしてこの映画の主人公の一人の少女ケリーアン(9歳)には、ポビーとディンガンという二人のイマジナリー・フレンドがいたのです。
あくまでも空想の中での話なので、周囲の人達、特に親には見えるはずもなく信じてもらえません。お兄ちゃんのアシュモールも初めは信じていませんでした。しかしケリーアンのあまりに真剣なまなざしに、心動かされたアシュモルは彼女の思いを認めたのです。映画では描かれていませんでしたが、兄のアシュモルもきっと心のどこかでおなじような体験をしたことを思い出していたのではないでしょうか。
大人になるともうすっかり忘れていますが、人は誰でもまず自分の心の中に「自分でありながら自分ではない誰か」を見つけ、その人と関わることで「自分と言うもの」に気が付くようになるのです。最初にも触れたジブリの「マーニー」や「千と千尋の神隠し」の物語など、まさしく、その年齢の少女の心の中の、現実と空想の狭間に産み出されたファンタジックな経験を物語にしたものだと思いますね。
そしてそういう体験の中の友人との別れを通じて、子どもは空想の世界から現実の世界へと新たに産み出されていくのです。そしてその別れと現実世界への導き手となるのが、「父親」の役割。この映画でも、空想の友人ポビーとティンガンを見失わせるきっかけとなたのが、父親でした。「目に見えているものだけがすべてじゃない」ということを大切にしながら、しかし一方では「我々は地に足をつけて現実を生きざるを得ない」存在であることを知らせることも、父親の果たす役割、また子どもが大人になって行く通過儀礼の役割かもしれませんね。
殺伐とした家庭に愛を求めてさまよう・・・
ママは何処へ行ったの?
「ママに会いたい」・・・
『ぼくらの旅路』

以前日本の映画で「誰も知らない」という映画がありました。都内の2DKのアパートに4人の兄妹が誰にも知られずにひっそりと暮らしていました。学校にも通ったことがなく、母親はわずかなお金と書置きを残して姿を見せなくなったのです。その後の漂流生活を当時少年だった柳楽優弥くんが見事に淡々と演じていました。当時社会に与えた衝撃は大きかったと思いますが、しかし実際は現実の方が数倍も過酷だったのです。
このような映画はほかにも、私が見ただけでも、たとえば韓国映画の「冬の小鳥」
さらにフランス映画の「ある子供」
と様々な作品が残されていますが、この映画「ぼくらの旅路」も同様に、見ているだけで切なく胸が締め付けられるような作品でした。
作品の設定はやはり母親からの養育放棄(ネグレクト)に当たるのでしょうが、その過酷な日々の中でも10歳のジャック少年は必至で生き抜いていきます。弟のマヌエルはまだ6歳なので、何もわかっていないようです。その弟の世話を一人で見ながら、母親が遊びに出かけていない寂しさを表情にも出さずに堪えています。
行政もその状況を理解していて、ジャックはやがて児童養護施設へ引き取られていきます。そこにはジャックと同じような境遇の子供たちが集団生活をしていますが、彼らの怒りや悲しみは様々な問題行動として噴出していきます。そこを何とか生き抜いたジャックは、一人母のもとへと歩いて戻ろうとするのです。
暴力や心理的虐待だけでなく、ネグレクトという形の虐待は子どもたちの魂を傷つけます。しかしそれでも子どもたちは親の元へと戻りたいという思いを抑えることができません。そして何とか戻ったとしても、そこに待っているのは以前と少しも変わらない状況・・・。
この映画の宣伝を見ると「突然消えた母親を捜すため旅に出た兄弟の成長を描くドラマ」と書かれていましたが、そんな甘いものではありません。結局彼らにとって戻らざるえ終えないところは、母親のところではなくジャックが逃げ出してきたはずの児童養護施設でしかありませんでした。
なんとも切ない映画ですが、現実はこれをもっと超えている厳しさではないかと思います。そういう意味で、目をそらしてはいけない映画だとつくづく感じました。
見るたびに、ため息が出てきてしまう・・
『ある子ども』
このDVDを見るのは2回目なのですが、見るたびにタメ息がでます。
タイトルは「ある子ども」
タイトル通り、主人公は年齢的には青年の域に入っているのかもしれませんが、その内面はあきらかに子ども。と言っても発達に問題があるということより、家庭環境の影響や社会における青年の閉塞感が彼らを大人にさせないのでしょう。甘えとそれを受け入れられない恨み。そして他人を信じることができず、信じられるものはお金だけ。
主人公は職もなく、家庭からも切り離されたのか、川岸の廃屋に寝泊まりして、日々をなんとなく過ごしている青年。彼は日々の小銭稼ぎに年下の手下を使って万引きや窃盗を重ねています。本当の愛情というものを体験したことが無いのでしょう、小遣い銭に困った彼は、彼女との間に生まれたばかりの息子を人身売買の組織に売り飛ばしてしまいます。
それを聞かされた彼女はパニックになりますが、その彼女に「また、(子どもは)できるさ」と軽く言い放ってしまうのです。自分の立場を守るためには嘘に嘘を重ね、全く良心が痛まない、そんな青年。この映画が描いている状況は、今や世界中で見受けられる姿ではないでしょうか。もちろん日本でも。
その原因を彼ら自身に求めたり、家庭環境に求めたり、あるいは社会に、時代に求めることはできるでしょう。しかし問題は何が原因か、ということよりも、「今、どうすれば良いのか」ということなのかもしれません。仮に家庭環境や社会、時代に原因を求めたとしても、それを変えていく解決策はすぐには見当たりません。
一番手っ取り早いのは、彼ら自身に原因を求め、やれ「行為障害」だ、「反抗挑戦性障害」だ、「反社会性人格障害」だ、挙句の果ては「発達障害」だ、と言って切り離したり特別扱いして終わってしまう、という方法なのでしょう。しかし、レッテルを貼ったからと言って、何も解決していないのは言うまでもありません。精神医学や臨床心理学がその片棒を担いでいるとすれば、無責任極まりないかもしれませんね。
レッテルを貼ることよりも、彼ら・彼女らに直接関わる営みをすることが大切なのかも。色々なことを深く考えさせられる映画です。
今の私の人生があるのも、両親が私を捨てたおかげです。
『冬の小鳥』
韓国映画の「息もできない」と言う作品があります。いずれ取り上げる予定ですが、圧倒的な迫力で描ききった映画でした。そしてこの「冬の小鳥」も同様の意味で圧倒的な迫力を感じさせてくれます。
両者に共通するのは、どちらも監督の実体験に基づいた映画である、と言うことです。
この映画の脚本・監督は ウニー・ルコントさんは、韓国生まれでありながら、父親に捨てられカトリック系の児童養護施設で9歳まで暮らしました。その後フランス人の家庭に養女として引き取られ、成人するまでフランスで暮らします。
この「冬の小鳥」は、そのウニ監督の実体験をジニという女の子の目を通して再体験することで、自分の過去と現在を確認した映画であると思いました。
さて、ストーリーは、大好きな父親に全く知らない児童養護施設に置き去りにされたジニ。
父親は必ず自分を迎えに来ると強く信じるジニは、頑なに養護施設の生活や周囲の人たちになじもうとせず、反抗や抵抗を繰り返します。しかし待っても待っても、その日は来ません。笑うことも忘れ、感情を押さえ込んでいくジニ。
しかしいろいろな仲間との交流を通して、絶望に立ち向かうジニの心の中で少しずつ変化が起きていきます。その変化が、見事なまでに象徴的な行動を通じて表現されます。
ネタバレになってもいけませんが、この「死と再生」の通過儀礼を思わせる象徴的なエピソードには、私はとても感動しました。
最後にウニ監督はこう言われています。
“ジニはたった一人世界に取り残されてしまいますが、そこから新しい人生を生きていくことを学びます。
これは愛する父親を失ったからこそ学びえたことです。
今の私の人生があるのも、両親が私を捨てたおかげです。
同時に「どうして親が子を捨てられるのだろうか」という問いかけも数え切れぬほどしてきました。
ありがたみと捨てられた痛み。
実の両親にを思い浮かべると、コインの裏表のような感情が交差します。”
虐待の中でも一番残酷だと言われる、ネグレクト。
しかしそのような状況の中でも人間は生き延びて、傷を抱えながらも成長していくのだ、ということを感じさせてくれた映画でした。もし機会があれば、一度見て下さい
疾風怒濤の思春期に荒れ狂う彼らは何を求めているのだろうか?
ヒリヒリする日々を送る少女たちの日々をあがいた作品
『少女』
一歩間違えば、深い闇に背後から落ち込んでいくような、ヒリヒリする不安な日々を描いた作品「少女」を見ました。
実は原作は湊かなえさんだということや、すでに有名な作品本屋に山積みの小説だったということも、不覚にも全く知らず、単にネット上の映画の紹介文を読んで興味が湧いて見に行ったのでした。でもそれは大正解!!
なにしろストーリーの展開の中にさまざまな伏線が張られていて、そうとは気づかずにみているとあっと驚かされながら物語が深く展開していきます。さすが湊かなえさんだと思われましたが、先に原作を読んである程度予備知識があるよりも、私にとっては新鮮な出会いでした。それにしてもトリッキーな仕掛けなので、ちょっとできすぎという感じもしないではないのですが、それよりも何よりも主人公2人の女子高生役の危うげな艶というか女子高生の不安定さを見事に醸し出されていたと思いましたね。
ネタバレになってしまうと面白さ半減なので、具体的に説明できないのがもどかしいですが、思春期の年代の「生と死」のテーマから、学校での「正義と悪」のテーマ、「性の持つ危うさ」などなど、まさしく「少女の持つ幻想のような危うさ」と「脱皮を遂げる『さなぎ』の年齢の身動き取れない苦しさ」が感じられましたね。
なお主人公二人は本田翼さんと山本美月さんというフレッシュで本格的なお二人。年齢的にもイメージもぴったりでした。私がスクールカウンセラーとしてよくお会いする子どもたちも、中高生の思春期年齢。大人でもなく、子どもでもない危うさと同居している年齢です。なんだか彼らとダブるところもあり、とても身近な映画でした。
それからこれはびっくりしたのですが、途中に出てくる冴えない会社員にあの、稲垣吾郎さん。これまたなんというか、浮遊感があって危うげで身元のしれない陽炎のような不思議な香りを出されていました。
自分で自分に叫ぶんだ!
「みんな、がんばれ!」
『ヒミズ』
タイトルの「ヒミズ」とは「日不見」と書いてモグラの意味だと言うことです。暖かい日を浴びることがかなわずに、自分のこころの中に沈静していく存在、と言う意味かもしれません。コミックが原作ですが、映画ではストーリーも多少異なります。
ネタバレしても困るのですが、家族から疎外され、拒否され、あるいはもっと積極的に抹殺されようとしている似たような境遇の二人の中学生、住田祐一(染谷将太、力演!)と茶沢景子(二階堂ふみ、彼女も素晴らしい!)をめぐるストーリーですが、そこに東日本大震災の風景がオーバーラップし、「人が絶望の中でも生きぬくためには何が必要か」「生きると言うことの意味」など、考えさせられる映画でした。
この「ヒミズ」という映画からは、人間が生きるためには暖かい光=父親・父性と暖かい大地=母親・母性に包まれて心の中に芽生え育つ安心感や自信や自尊心が必要なのだと改めて感じさせられます。
しかしそれがかなわない時、人を信じられなくなり、自分が生きている意味さえわからなくなってしまいます。主役の住田祐一を演じた染谷くんは、そういう「凍りついたまなざし」を見事に表現していました。
冒頭に原作とは監督のスタンスが違う、と書いたのは、時期的に重なったと言う意味もあるのでしょうが、基本的に東日本大震災の被災者と重ね合わせて、絶望の中を生き抜く人間への希望を描いているというところです。
私は涙なしには見られませんでしたが、最後のシーンで、「住田、がんばれ!」「住田、がんばれ!!」とふたり叫びながら走っていくシーンにはとても共感するものがありました。
虐待やDVやいじめなどさまざまな厳しい状況で生き抜いているみんな、阪神大震災や東日本大震災、あるいはさまざまな状況を生き抜きつつあるみなさん、そしてあなたや、私。どこかの誰かに無責任に言われるのではなく、自分自身に向かってこころの中で叫ぼう。
「みんな、がんばれ!」
なぜ、彼は弓を引いたのか?
『少年は残酷な弓を射る』
DVDのジャケットだけ見ていると、
なんだかイケメンがキューピッドの矢を射るようなイメージがあるかもしれませんが、ところがどっこい、この映画は現代社会の大問題を描いた問題作だと思います。
作家の母親を持つ息子のケヴィンは、なぜか幼い頃から母親にだけ反抗を繰り返し、心を開こうとしない。幼い頃は自閉症も疑われたが、はっきりとしない。
とにかく母親にだけはなぜか思いきり反抗的なまなざしと、ある種知能犯的な態度を崩さないのです。父親に対しては素直な良い子を演じるのですが、その二面性は周囲の者には気づかれていません。
やがて美しく、賢い、完璧な息子へと成長したケヴィンであったが、母への反抗心は少しも治まることはなく、用意周到で悪意に満ちた行動で、家族を破壊し、最後には残虐な大事件を起こしてしまいます。
この息子を、いわゆる生れついたサイコパスと捉えるのか、母親との関係の中での愛着障害ととらえるのか、発達の過程での素行障害や反抗挑戦性障害ととらえるのか、
そういう問題は横に置いておきましょう。
ただ、現代社会でメディアを賑わす残虐な事件(少年Aの事件や黒人殺害の白人少年の事件に代表される)と共通する背景をもっているのだろうとは思わずにはいられないのです。
こういう子供たちを前にしたとき、私たちは何ができるのか???
そして何よりなぜこういう子供たちが出現してきてしまったのか??
目の前に大問題を突きつけられているのだけれど、答えられない・・・・・。
ただ、最後のシーンで、私はわずかながら希望を感じました。ネタバレになってもいけないので説明出来ないのが残念ですが・・・。
ちなみにこれはサイコホラーでもなくスプラッター映画でもなく、純粋に親と子の関係の中での「愛着」のありようについて描いた映画だと思います。
<神戸新聞のマイベストプロに掲載されているコラムはこちら>
☆リンク☆
■ 聴覚障害児・者関連のカウンセリングならオフィス岸井へ
http://deaf-officekishii.jimdo.com/
■ 心理カウンセリングのフィーチ
サイトトップURL:https://feech.net
当サイトの紹介記事URL:https://feech.net/counseling-rooms/kobe/